『今年も きたかよ さくらんぼ』
80代の女性Hさん。
神経心理検査の書字課題より。
山形出身のHさんとは同郷ということで話が盛り上がり。
その後、標語のような作文をしてくださいました。
毎年6月になると田舎のきょうだいから嬉しい贈り物が届くそうです。
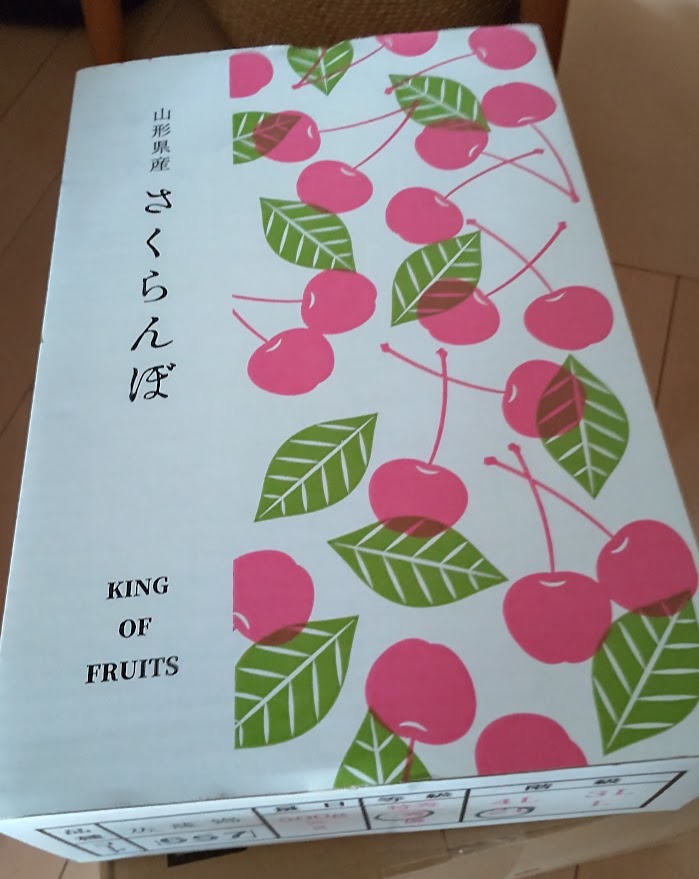
高齢の方々とやりとりする日々の中で、印象に残ったできごとを綴ってみました
『今年も きたかよ さくらんぼ』
80代の女性Hさん。
神経心理検査の書字課題より。
山形出身のHさんとは同郷ということで話が盛り上がり。
その後、標語のような作文をしてくださいました。
毎年6月になると田舎のきょうだいから嬉しい贈り物が届くそうです。
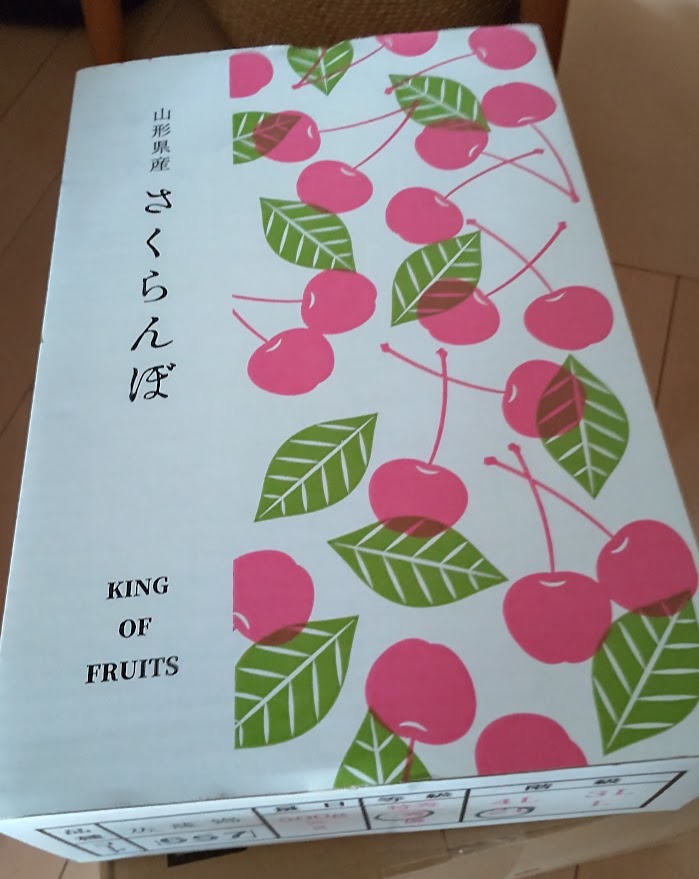
『私の身体について こんなに想ってくださるなんて 感謝です』
神経心理検査の書字課題でこのように綴った80代の女性Tさんは、続けて静かに次のように話されました。
「家ではごはん作って出して…、毎日いろいろみんなのお世話して。自分の身体のことを『どう?』なんて言ってくれる人はいません。でもそういうことを昔と同じようにできてるってことかなって思って…。私は、やってくれて当たり前と思われてるほうがいいのね。できてる、ってことだから」。
そして「おかしなものね、歳を取ると…」と言ってふふふと笑いました。
私がTさんの体調を心配して何気なくかけた言葉に、Tさんがふと感じたこと、気づいたことを述べ、私はそれを聴く…。こういう時間を大事にしたいです。

『記念になるように答えたいです。』
90代の女性Tさん。
神経心理検査の書字課題より。
重い難聴のあるTさんは、PC画面に表示された教示文を読みながら、真剣に検査を受けられました。
「耳が悪いから、人と会話しても互いにつながらないのが一番の悩み」とおっしゃっていましたが、「今度ひ孫が生まれるの。ものすごく希望」と明るく前向き。
一生懸命答えてくださったので、ここにも記念します。

少し時間に余裕ができたので、旅でもしようかと思いました。
どこに行こうか迷ったのですが、そうだ、四万十川!と思い出しました。
前から行ってみたかったのです。
わくわくといろいろ手配して、春の四万十川を見に行く小旅行。
高知はもちろん、四国も初めてでした。
川を巡るバスツアーを申し込んで、朝行ってみたらなんとその日の客は私1人!
初め恐縮してしまいましたが、気さくな女性の運転手さんで、すぐにリラックスできて、時におしゃべりも楽しみながら、思いがけずなんとも贅沢な貸し切りバス状態。
いくつもの沈下橋に降り立ったり、屋形船に乗ったり、美しい景色を心から満喫しました。
屋形船ではさすがに1人ではなく、長崎から来たという70代くらいのグループと一緒になり、写真を撮ってあげたり撮ってもらったり。それもまた楽し。
その日の夜は、運転手さんからもぜひにとすすめられた、地元の居酒屋へ。
カツオやウツボのたたき、川エビのから揚げ、ゴリの佃煮などを地酒とともに堪能しながら、バスツアー楽しかったなあ、としみじみ。
味はもちろん、接客もとても気持ちのよい、活気あるお店で、地元客でとても賑わっていました。
大きな扇形のカウンターの端っこから、何とはなしに店内を眺めていると、50代くらいの男性と、70~80歳くらいの女性が並んで食事をしていて、そのお顔がそっくりで、どこからどう見ても親子(笑)。ときどきここへ来て食事してるんだろうなぁという雰囲気で、なんかいいなあと、これまたしみじみ。
私も地元民、というていで飲んでいたつもりでしたが、お会計のさい「どちらから?」と聞かれ、観光客とバレバレでした(笑)
久々の一人旅。やっぱりいいなあ。

「まっていた 春が来た 来た。」
80代の女性Sさん。
神経心理検査の書字課題より。
その後から私は、春らしい光景に出会う度に、
わくわくした気持ちで「春が来た、来た」とつぶやいています。
もちろん心の中で、です。

「今日は色々な検査をして頂いて
嬉しいやら 結果が心配になるやら
大切な1日です。」
80代の女性Hさん。
神経心理検査の書字課題より。
いろいろな気持ちが入り混じっているようですが、
大切な1日になったのだとしたらよかった。

前回、もの忘れの程度など様々な認知機能を調べる神経心理検査の課題の1つに文章を書いてもらう書字課題というのがあるとご紹介しましたが、たった一文、書いていただくだけで、その中にも非常にいろいろな個性が見え隠れします。
「今日は病院に来ました」
「今日はいい天気です」
などと当たり障りのないものも多いのですが、はっとさせられるような文章に出会うこともあります。
「この頃、私は何かおかしい」
「私はだんだんだめになりそうです」
などと、もの忘れに伴う不安な胸の内を文章にされる方も少なくありません。
「家族に迷惑をかけています」
などと周囲への申し訳なさをしたためる方もいらっしゃいます。
そんなときはとても切ない気持ちになります。
その一方、思わず顔がほころんでしまうような、ユーモアやセンス溢れる文章と出会うときもあります。
先日検査にいらっしゃったNさんは、3年ほど前に中等度アルツハイマー型認知症と診断された84歳の女性で、今回の長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)とMMSEという30点満点の簡易検査でそれぞれ9点、13点でした。
中等度くらいの認知症になると、検査においてできない課題が多くなるため、嫌になってしまう方も多いのですが、Nさんは最後まで心から楽しそうに、やる課題、やる課題、興味津々といった感じで目をきらきらさせて取り組んでくださいました。
そして件の書字課題ですが、Nさんは少し考えてゆっくりと、用紙に縦に「今日のお知らせ」と書きました。
これだけでは文章ではないので得点になりません。
Nさんはまた少し考えて「娘の」を加えて「今日の娘のお知らせ」に修正。
それでも主語・述語がないと文章にならないため、残念…と思っていると、Nさんは改行して「今日のお昼ごはんは」、そしてまた改行して「ゴーセーですよ!」と書き加えました。
「今日の娘のお知らせ
今日のお昼ごはんは ゴーセーですよ!」
これならOK! どころか、なんてセンス! と私は感動しきり。
びっくりマークもとても可愛らしく書けています。
文章が書ければ1点、書けなければ0点ですが、10点くらいあげたいところでした(もちろんしていませんが)。
Nさんは同居する娘さんの書くメモを頼りに生活されています。そんな娘さんからの「お知らせ」はお昼ごはんに関することでした。
「いつもは残り物とかで簡単に済ますんですけどね。こういう(豪勢な)ときもあるんです」と笑ってNさん。
Nさんは3分前のことも忘れてしまいますが、こういう文章が書けます。
そこも記憶ですが、こういう記憶は頭の中のどこにどうやって存在しているのか不思議です。
Nさんはそんな文章を書いたことも忘れて、私の手引き歩行で娘さんの待つ待合室までゆっくりと戻られました。
そのNさんが3年前に書いた文章は
「このたび面白い経験をさせて頂きました。ありがとうございます」。
そして今回も何度も「ありがとうございます」と述べられていました。
こちらのほうこそ「ありがとうございます」。

可愛らしい花が咲きました!
5年ほど前から年1回の神経心理検査を受けられているNさん(男性)は、大正15年生まれの97歳。
この日も雨上がりの道をお一人でゆっくり15分程歩いて検査を受けに来られました。
もう笑顔が素敵で、いつもNさんとお会いするといっぺんで幸せな気持ちになります。
<お若く見えますね>とお世辞抜きで申し上げると、「昔からうちは男は若づくりの家系なの」とのこと。
検査も一生懸命に、なおかつ楽しそうに受けられて、常ににこにこして、物腰も穏やかです。それでいて、壮絶な体験なども過去にされているのです。
滲み出る優しさと屈託のなさに、何というか、とてもきれいなものを見た、というような気持ちになります。もちろん優しい方はたくさんいますが、ここまで感じさせる方は本当に稀です。
何が違うのだろう…といつも考えさせられます。心根の本当にきれいな方は、ちょっとやり取りするだけで分かるというか、心が震えるような感動があります。いやいや大げさでなく。私もいつかこんなふうになりたい。なれるかな。目標です。
さてさて、神経心理検査には文章を書いてもらう書字課題というのがありますが、Nさんが今回書いたのは、「アメガヤンデ、タスカリマシタ」(表記ママ。以下も同じ)。
何だかチャーミング。
確かに朝方はけっこうな雨でしたが、すっかり晴れ上がりましたものね。
後で過去に書かれた文章を振り返って見たら、初回には「ねぶそくでボヤットして居る」。その後は「今日はよくねむれたよ」「キョウワヨイテンキデス」「おはよう きょうは仕事をしようかな」。そして前回が「キョーワ雨フリデコマリマシタ」。およそ1年毎ですが、何となく繋がっていて楽しい。
「皆から100歳までって言われて、おだてにのっているの」と笑っておっしゃっていましたが、100歳までどころか、その先もずっとお元気で。私にお手本を見せ続けてください。

部屋から見える夕暮れの風景。2023年もあと少し。
ある日の昼下がり、区が主催するオレンジカフェに10名ほどの高齢の方々が集っていました。
皆でおしゃべりをしていると、80代の男性がおもむろに、「そういえば、コウテイダリアって知っていますか?」と切り出しました。
「コウテイダリア? 知らないです」と私。
お一人の女性だけは知っていますよというふうに頷かれていましたが、他の方々は皆、首を傾げています。
男性は、「いやー、すごいんだよ。こーんなに伸びて、なんと5mくらいになるんだから! 5mの高さまで成長する花なんて皆さん、信じられますか!?」と身振り手振りを交えて話し、「いやあ、すごいんだよ」と興奮気味に繰り返されました。
「5m? 確かにすごい! コウテイって、皇帝ペンギンの皇帝ですね? エンペラー」と私も興味津々に身を乗り出します。
先程頷かれていた女性が、「皇帝ペンギン…じゃなくて皇帝ダリア、○○公園に植えられていますよ。確かこれから咲くんじゃないかしら」と教えてくださいました。
男性はつい先日、民家の軒先で見つけて初めて知ったらしく、「いやあ、自分は農学校を出て、植物には詳しい方だと思っていたけど、この歳になるまで知らない花もあるんだなあと、もうびっくりしたなんてもんじゃなくて」と、花を知ったのがまるでついさっきのように話されます。
私もそんなダリアがあるんだ! と感動しただけでなく、男性の感動ぶりにも感動してしまいました。
そんなふうに心が動く体験を、いくつになってもしたいものです。
ある男性がスマホで検索して皇帝ダリアの写真を見せてくださいました。
上品な薄ピンク色の花々が、青空に届くかのように凛とそびえていました。

仕事帰りに時々寄る、美味しい和食とクラフトビールのお店。
わくわくしながらまずはビールを選び、さてと、本日のお料理は…とメニューを見ると…ん?
耳慣れない名前がボードに書いてあります。
“ミズのボンボン”
みずのぼんぼん??
可愛い響き。でも何だろ。いろいろ想像が膨らみます。
謎のまま「すみません、ミズのボンボンって何ですか?」と尋ねると、「知らないですか? 知っていると思いますよ」と返ってきました。
「知ってる? 私、知ってる?」「ええ」「じゃあミズって山菜のミズですね。それは分かるけど…」
聞くと、ここの女性店主、つい数日前に山形のとある村の鄙びた温泉宿にふと思い立って泊まりに行ったとのこと。
そこは私の生まれた町からもそう遠く離れておらず、かなりの田舎で豪雪地。
もちろんまだまだ雪は降っていませんが、何でそんな僻地(あ、でももちろんとてもいい温泉地ですよ)を選んだのかも謎。それはここでは置いといて…。
泊まった翌日、彼女は朝市に出かけたそうです。
そこで、こぶのような赤い実をつけた見慣れぬ山菜を見つけ、そばにいた高齢の女性に「これ何ですか?」と尋ねると、そのおばあさんが「知らねの(知らないの)? ミズのぼんぼん」と答えたとのこと。
おばあさんの口真似をする店主の山形弁のイントネーションがばっちりで、「ぼんぼん」の後ろの「ぼん」を強く言うところがすごく可愛くて、思わず「かわいい~」と言うと、店主も「そうなのよ! 響きがすごく可愛くて」そのミズのぼんぼんをたくさんお買い上げ。もちろん響きが可愛いだけでなく、おばあさんから「うんまい(おいしい)よ」とお墨付きをもらったからなのですが。
さっと茹でてからそばつゆなどに一晩漬けるだけで美味な1品になります。
この日は白だしに漬けたものをいただきました。
瑞々しい歯ごたえで、とろっとした粘りとわずかな苦みがあるのが絶妙でくせになる味。箸が止まりません。
ミズのぼんぼん。「知っていると思いますよ」と言われましたが、実は私、知りませんでした。山形在住の頃、ミズは初夏に茎をお浸しとかでよく食べていたのですが、秋の実を食べたことはなかったように思います。
名前もしかり。ただこのネーミングはこの土地ならではのもののようで、調べると秋田とかでは「ミズの子」とか「ミズこぶ」と呼ばれているよう。でも私は「ぼんぼん」が好きだなあ。
故郷である山形の山菜の実を、東京のお店で食しながら、初めてとはいえ懐かしいような気持ちになりました。
そして、「知らねの? ミズのぼんぼん」と言った朝市のおばあさんを想像し、そのフレーズを何度も心の中で繰り返しながら、他のお料理も、ビールも堪能しました。
ちなみにこの日飲んだのは長野と奈良のクラフトビール。ごちそうさまでした。
